toriR blog
2025年鳥学会参加しました(1日目)
日本鳥学会2025年度大会に参加し、黒田賞受賞の岡久雄二さんによる保全鳥類学の講演や、シンポジウムで語られたウトウ研究など、多くの刺激を受けました。動物園が担う生息域外保全の重要性や、世代ごとの研究スタイルの違いを感じつつ、若手の国際的な成果がこれから学会をどう広げていくのかに期待を寄せています。概要
2025年9月北海学園大学であった日本鳥学会に参加してきました。報告件数は、口頭発表は2パラレルセッションで72件、ポスター発表は一般141件の小中高校生による21件あり、2日間で1時間ずつのコアタイムでおおよそ半分ずつの説明がありました。最終日に公開シンポジュームでした。その中で印象に残った発表を備忘録として記録に残しておきたいと思います。その他、10件の自由集会という会員企画の特集がありましたが、時間の関係で参加できませんでしたのは残念です。
全般的な印象は、黒田賞を受賞された岡久雄二さん記念公演がよかったです。「科学と実務をつなぐ保全鳥類学の実践」というタイトルで佐渡島でのトキの保全と、現在在籍されている人間環境大学での本州アカモズの保全について熱く語っておられました。なるほどなと思ったのは、日本鳥学会も野鳥の会も一般的には動物園での飼育も保護鳥もあまり話題にはなりませんが、絶滅危惧種の生息域外の保全という観点でとても大きな役割を担っていることが理解できました。しかも動物園が飼育展示しているのはコレクションだけではなく、保全の役割がとても大切でこれには短時間勝負という視点が欠かせないということだそうです。飼育ならではの知見も豊富に持っておられるので、もっともっと学会などで保全の観点だけでなく生態や生理機構など学会での報告と意見交換があるといいと思えました。個人的繋がりでは人間環境大学の卒業論文をトリルラボがツール提供でサポートしたこと、先生が大学時代に照ヶ崎(神奈川県)にアオバト見学でお越しになった時に、ケーキを一緒に食べたことが、思い出されます🤭。
公開シンポジュームは北大構内のホールで4名の大御所が登壇されました。個々の研究史としては抜群に面白かったです。特に綿貫会長のウトウの餌の分析が11年周期の寒冷・温暖変化による餌資源変化の影響を受け、育雛成績に影響が出るというお話は北東アジアの食物連鎖の生態系に関するスケールの大きなもので非常に興味深かったです。ただ、「鳥学が牽引する現代生態学―鳥の研究は面白い!」と冠しシンポでしたが、現代生態学に鳥類学が、更に日本鳥類学が果たした寄与は全面に出てこなかった感じです。そこには時代背景として、メジャー誌に論文を出すことが最も大きな目標とされた世代の価値観が反映されていたのかもしれません。私は物理や工学の学会での経験を持つためか、日本の鳥学の議論がやや内向きに感じらこともあるのですが、それでも今の若手研究者は、すでに世界的な成果を挙げていますので、これからどんどん成果報道に触れたいものです。
今回も準備に尽力された事務局スタッフの皆さまに感謝します。そして、発表や議論を通して多くの学びを与えてくださった研究者の方々にも、心からの謝意を表したいと思います。
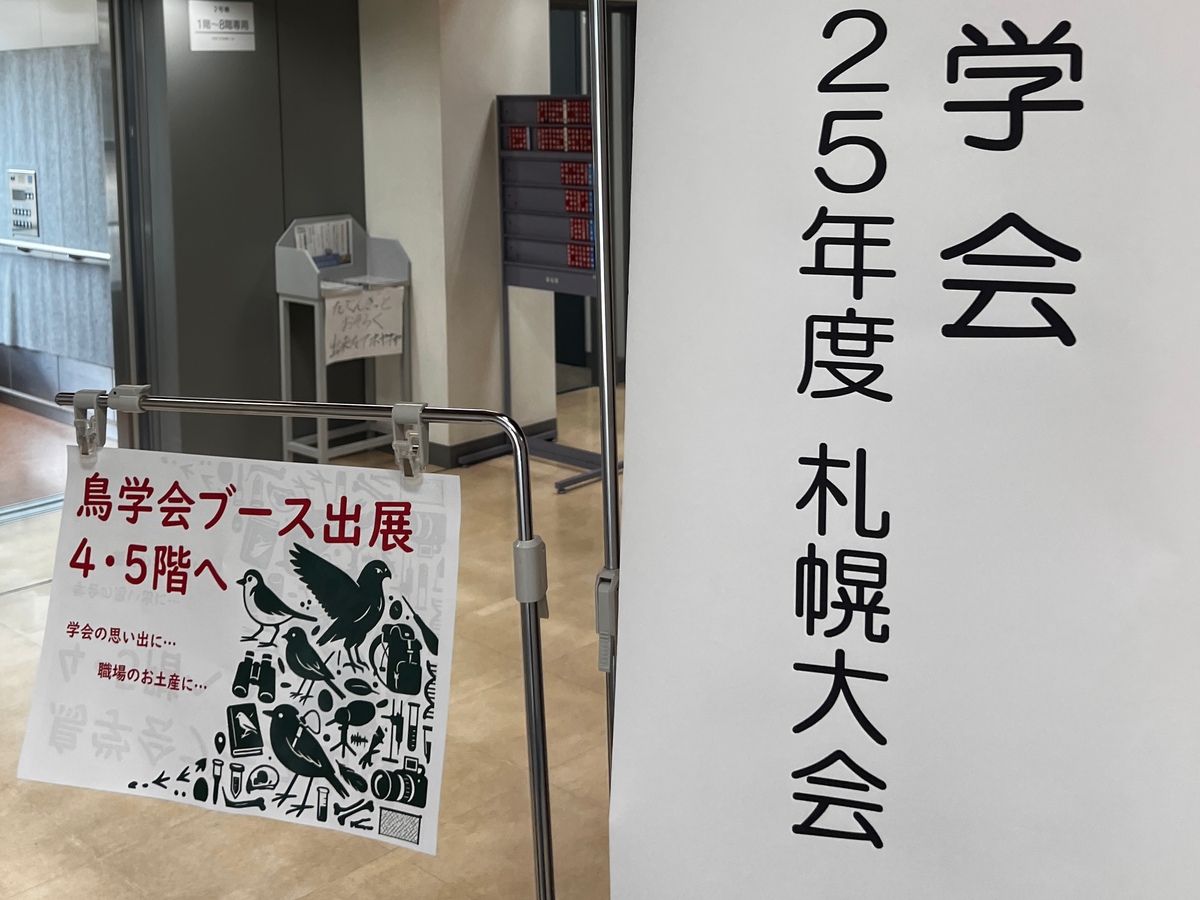
day1 [2025-09-13]
場所:北海学園大学
<口頭発表>
インドネシアの越冬地におけるハチクマの環境選択と気候変動の影響
Syartinilia Wijaya・Aryo Adhi Condro (ボゴール農科大)、○樋口広芳 (慶應大)
- 毎年、森林消失が進んでいる
- 山火事の影響を大きく受ける(人為的起因山火事)
- 中核/地域は周辺深刻
- 気候変動がハチクマ生息分布に及ぼす影響
- SSP2(そこそこ対策した)/SSP5(何もなし)で越冬地の消失が大きく進んでいく。
- 渡りの距離が増える
感想:
- 越冬地や中継地の保全は緊急を要することがよくわかりました。
サシバは同じ繁殖地と越冬地を利用するのか?
〇鳥飼久裕(奄美野鳥の会)・東淳樹(岩手大)・井上剛彦(ARRCN)・遠藤孝一(WBSJ)・出島誠一
(NACS-J)・内藤アンネグレート素(ARRCN)・葉山政治(WBSJ)・藤井幹(WSPB)・松永聡美
(WSPB)・山﨑敦子(ARRCN)・山﨑匠(ARRCN)・与名正三(奄美の自然を考える会)・和田のどか
(ARRCN)・山﨑亨(ARRCN)
- 奄美で全部20羽のサシバにGPS装着(メス成鳥のデータ)
- 全部東日本に繁殖期間に戻った
- 春は9日間
- 秋は中継経由して(〜3ヶ月)56.8日
- 移動開始はばらけているが到着は2週間程度の差
- 越冬地の同じ場所に戻ってくる個体多し
- 繁殖地も同じ個体が多い(狭い範囲で同じ)
- 繁殖開始はバラバラで緯度とは関係ない
感想:
- GPSを使った研究はもう当たり前ですが、その結果はやはり面白い。奄美の越冬サシバの繁殖と渡りはまだまだ謎だらけです。
北海道で繁殖するヨタカの渡りルート
発表者
○山浦悠一(森林総研)・雲野明(道総研林試)・河村和洋(森林総研)・先崎理之(北大)・佐藤重穂(森林総研)・大谷達也(森林総研)・Greg Conway(BTO)
調査方法
調査地: 北海道道央の幼齢人工林
対象: 2024年繁殖期に捕獲したオス3個体
装着機器: 衛星発信型GPSロガー(Lotek社製 PinPoint Argos75 日本版)
- 装着方法: leg loopハーネス
- 重量: 体重の3.8〜4.6%(約4.0g)
測位期間: 2024年8月1日〜11月30日(5日ごと)
主な結果
繁殖期は10kmの行動圏
3個体は 9月末〜10月中旬に繁殖地を出発。
南西諸島を経由して移動。
11月末〜12月中旬にボルネオ沿岸低地に到着し、越冬地として利用。
一部にプランテーションを含む行動圏を確認。
帰路はインドシナ半島〜朝鮮半島経由。
渡りルートは 環状ルート を形成。
越冬期の行動圏は繁殖期よりも小規模であった。開放地ではなかった。
北海道で繁殖するヨタカの越冬地は、ボルネオ沿岸低地であることが初めて明らかになった。
渡りルートは南西諸島・インドシナ半島・朝鮮半島を経由する 環状ルート を描く。
今後の保全においては、日本だけでなく 越冬地の土地利用(プランテーション含む) との関わりを考慮する必要がある。
琉球列島では過去200羽の夕方見たという記録があった(油が乗っている美味だとか)
ケリの親子・兄弟・ペアのGPS追跡
発表者
脇坂英弥・脇坂啓子(関西ケリ研究会)
調査方法
- 調査地:京都府・巨椋池干拓地の農地
- 対象:2025年繁殖期にGPS装着
- 親子(親1+幼鳥2)×2組
- ペア(成鳥2)×1組
主な結果
親子・兄弟
家族a:幼鳥2羽は82日齢・84日齢で出生地を離れ、別々に行動。兄弟は別日に同じ2km先に滞在。
家族b:幼鳥は76日齢で出生地を離れ、79日齢まで親と同地点で過ごした後移動。
親鳥は巣近傍や2km圏内に滞在。
ペア
- 抱卵失敗後も2羽で共に行動。
農地以外、競馬場とグランド、パチンコ屋に夜間(照明の切れている時間帯)によくいるものもいる
考察
- 幼鳥が別々に行動するのはリスク分散の可能性。
- ペアが行動を共にするのは翌年繁殖に向けた戦略と考えられる。
- 幼鳥自立後の滞在地から、家族関係の継続性に示唆が得られる。
続・「2羽どまり」の謎 ― 九州で越冬なわばりを共有するノスリの遠隔追跡
発表者
中原亨(北九博)・伊関文隆(希少生物研)・吉岡俊朗(おおせっからんど)・長井和哉(岩手大)・雀ヶ野孝(長崎大)・大槻恒介(長崎大)・中山文仁(自然研)・山口典之(長崎大)
背景
ノスリ(Buteo buteo japonicus)は繁殖期につがいでなわばりを共有するが、越冬期は通常単独でなわばりを持ち排他的である。
しかし九州では、2個体が敵対せず隣り合って止まる「2羽どまり」が観察されてきた。
ノスリでソーシャルキャリーオーバー効果の有無確認が同期
調査方法
- 調査地:九州の越冬地
- 対象:2羽どまりを示す4組(8個体)
- 手法:捕獲してGPS装置を装着し、同時遠隔追跡
主な結果と考察
4組すべてが雌雄ペアで越冬なわばりを共有。
少なくとも3組は複数年同じ場所で確認。
日中の移動の同期や夜間の塒(ねぐら)の共有を確認。
ただし繁殖期の渡り先は雌雄で異なっていた。つがいを作っていない
越冬地での「2羽どまり」は複数年継続する親密な関係を示す。
しかし繁殖期は別個体とつがいを形成しており、社会的つがいではない。
越冬期特有の関係性が、生活史全体の社会構造に影響している可能性がある。
GPS発信機によるイヌワシの追跡結果
発表者
中島拓也・阿部學・橋本哉子(ラプタージャパン)
結果と考察
- 生分解の糸で3年で脱落するような糸を選定
- 2018年9月〜2020年6月にGPSで成鳥1個体を追跡(取得データ150点と少数)。
- 行動圏は全期間で約112㎢、2018年9〜11月で約90㎢、2020年4〜6月で約5㎢。
- 標高範囲は560〜2050mで、峰付近に多く分布し、低標高域(河川周辺など)ではほとんど確認されなかった。
- データは限られるが、イヌワシの利用環境は山岳部に偏る傾向が示唆された。今後は捕獲再開と高精度データの蓄積が必要である。
- クマタカと同所的に生息場所では高低差の棲み分け(イヌワシは山頂付近、クマタカは川沿い)
- 課題:捕獲法の最適化
スワンプロジェクト ― 鳥類の渡り追跡公開と市民科学
発表者
嶋田哲郎(伊豆沼財団)・小西敢(クッチャロ湖水鳥観察館)・李国政・史国?(ドルイドテクノロジー)・樋口広芳(慶應大)
結果と考察
- 2023年12月に始動。オオハクチョウ・コハクチョウ39個体にカメラ付きGPS「スワンアイズ」を装着し、全個体に愛称を付与。
- 位置情報と画像を1日3回取得でき、ほぼリアルタイムで公開。ハクチョウのいた場所や見た景色を誰でも確認可能。
- 多言語ウェブサイトやスマホアプリを通じてアクセスでき、現地案内や観察記録投稿(X連携)により市民参加を促進。
- この仕組みによって、ハクチョウ類の1年の暮らしぶりが可視化され、市民科学的な見守り体制が国際的に構築されつつある。
- 越冬地では2番舗の田んぼをよく使っていた
- 中継地(北海道):麦畑、レントコンをよく利用
クロツラヘラサギ調査で見えた小型ドローンの有効性と注意点
発表者
小久保守晃(葛西のクロツラ)・北村亘(葛西のクロツラ/東京都市大)・木村成美(NPO birth)・上原文弥(葛西のクロツラ)
結果と考察
- 2025年2〜4月に葛西海浜公園「東なぎさ」で小型ドローンを用い、クロツラヘラサギの行動を調査。
- 日の出前の貴重な行動映像を空撮で取得。加えて、ハジロカイツブリの集団採餌やスズガモ・カンムリカイツブリ・カモメ類の映像も記録。
- 一部の鳥類はドローンを脅威と感じず予想外に接近することがあり、衝突リスクが判明。
- ドローンは鳥類調査に有効だが、安全距離の設定と衝突回避が必須であることが示された。
Ubilink Satellite System for Biotracking
Presenter
LI GUOZHENG(Druid Technology Co., Ltd.)
Results and Discussion
- Ubilinkは新しい衛星生物追跡システムで、従来のセルラーや衛星タグの限界を克服。
- 特徴: 衛星数の増加・広域カバレッジ・Intelink互換性・低コスト。
- Intelinkとの統合により、生態研究の応用範囲が大幅に拡大する可能性が示された。
- Nano 2(2g) : 2025/12
- Nano ?(1g): 2026/
感想:
- 1gの無線センサーが使えると小鳥にも応用できそう。衛星にしてwifiを張ることが研究インフラになりそうです。
気候条件の異なる移住先におけるメジロの繁殖生理学的応答
発表者
堀江明香(大阪自然史博)・平井仁智(岡山理大)・山内悦子(金城輝雄ほか、沖縄こどもの国・関連機関)ほか
結果と考察
- メジロを温暖条件(沖縄)と寒冷条件(岡山・大阪)で入替飼育し、雄の糞中テストステロン濃度を指標に繁殖開始時期を比較。
- 捕獲地そのままの飼育群では、濃度上昇時期が野外の繁殖期と一致。
- 移住群では、生息地本来の繁殖期ではなく、移住先の気候条件に応じた時期にテストステロン上昇が確認された。
- したがってメジロは気候条件に応じて繁殖ホルモン分泌を柔軟に変化させ、異なる環境でも繁殖適応が可能と考えられる。
- 日朝と気温に反応しているわけではない。日長さの増加量が伸びる+気温が上がっていく
- 周辺の音声の影響は?(社会的刺激)
感想:
- 子育て期間にできることとして発案されたとのこと、よく思いつくなー。分散先の環境変動に対応できる体内メカニズムは環境選好性の幅を決めているのかもしれません。
ルリビタキの発色を考える ― 換羽・生活史・発色メカニズムの視点から
発表者
森本元(山階鳥研)
結果と考察
- ルリビタキの青色は羽毛内部のスポンジ層による構造色が主な起源。
- 本種は「遅延羽色成熟(DPM: Delayed Plumage Maturation)」の典型例であり、若いオスはメスに似た褐色羽をまとい、成長とともに構造色の青へと変化。
- この羽色変化は換羽や生活史と密接に関連し、発色のメカニズムと行動生態を統合的に理解する上で重要。
- よってルリビタキは、構造色発色とDPMをあわせ持つ鳥種として、発色研究・進化生態学の好例といえる。
- 羽根内部のスポンジ層で構造解析で2Dフォトクリスタルモデルでシミュレーションで確認(2014)
- 体の部位で色を変えていくのはどうやって制御しているのかが今後の課題
感想:
- 羽根のスポンジ状構造が散乱することで青くなることをコンピュータシミュレーションで確認した話が面白かった。干渉だと単純に思っていたけど、穴のサイズと配置が決定的に重要だったのでしょうね。
トカラ列島における鳥類群集構造
発表者
安藤温子(国環研)・飯島大智(筑波大)・井上遠(IBRG)・佐藤望(IBRG)
結果と考察
- 2023〜2024年4〜6月、7島(口之島〜宝島)81ルートでラインセンサスを実施し、82種・5540個体を記録。
- アカコッコ:中之島・諏訪之瀬島・悪石島で確認、特に諏訪之瀬島で高密度。
- イイジマムシクイ:口之島・中之島・諏訪之瀬島・悪石島で確認、中之島・諏訪之瀬島で高密度。
- アカヒゲ:小宝島・宝島を除く5島で高密度。
- これらの結果から、トカラ列島における繁殖鳥類の分布特性が明らかとなり、島内スケールでの生息地選択や保全計画に資する基礎情報となる。
アカモズ放棄卵の救助と人工孵卵技術の試み
発表者
行本帆花・神谷頼杜(人環大)・間宮ふうか(人環大)・赤松あかり(長野アカモズ保全研)ほか
結果と考察
- アカモズ(Lanius cristatus superciliosus)は本州個体群が絶滅寸前であり、抱卵放棄が頻発。これまで放棄卵は救助されなかったが、緊急的保全策として人工孵卵を開始。
- 2023年から長野県内で放棄卵を回収し孵化・育成を試みた結果、2年連続で計22個体の人工育成に成功。
- 本研究はアカモズで初の人工孵卵事例であり、卵の救助体制・移送技術・人工孵卵方法を検証。
- 成果はヘッドスタート手法の有効性を示すと同時に、継続的保全のための技術課題を明らかにした。
- 37.8°で5分冷却を入れていた。
感想:
- 生息域外保全の最前線の話。頑張れ。
再導入コウノトリのなわばり防衛行動の性差
発表者
白井あやか・出口智広(兵庫県大/コウノトリ郷公園)
結果と考察
- 2023〜2024年、兵庫県豊岡市で繁殖した14つがいを対象に、なわばり侵入個体への防衛行動を観察・解析。
- 防衛行動には、直接攻撃とクラッタリング音による間接攻撃(単独・雌雄ペア)が確認された。
- 雌の独身個体が繰り返し侵入する事例があり、その定住の有無を解析に考慮。
- 多変量解析により、行動間の関係性や性差、ペアごとの差異が明らかに。
- 再導入コウノトリのなわばり防衛は、雌雄の協力と役割分担が複雑に絡み合う行動であり、性的対立ではなく協働的防衛戦略が示唆された。
再導入コウノトリ ― 配偶相手の決め手は何か?
発表者
出口智広・内藤和明・大迫義人(兵庫県大/コウノトリの郷公園)
結果と考察
- コウノトリの64%は未繁殖個体
- オスとメスの年齢は同年齢婚が多い
- 血縁認識なさそう(人為的近親婚を回避)、生地回帰性は明確にある
- コウノトリは長寿でmate fidelityが高く、配偶継続率は約90%/年。一方で成鳥の約半数は繁殖に至らない。
- 幼鳥は広く分散するが、繁殖地は出生地・放鳥地の近傍(数十km圏内)に集中。
- 2023年までに繁殖した96個体を対象に、配偶者選択要因として年齢差・血縁関係・出生地/放鳥地距離を検証。
- 解析により、配偶者選択は地理的要因(出生地や放鳥地の近接性)の影響が大きいことが示唆された。
- 再導入個体群の長期的存続を考える上で、分散パターンと局所的な配偶形成の関係が重要である。
再導入トキのコロニー崩壊のメカニズム
発表者
永田尚志(新潟大)
結果と考察
- 野外個体数550羽(32回の放鳥)
- 佐渡での再導入トキは2024年末に推定550羽を超えたが、2019年以降、密度効果により繁殖成績が低下。
- コロニー崩壊の要因は、種内干渉による繁殖開始の遅れと、捕食者誘因による捕食圧。
- 通常、崩壊したコロニーは繁殖失敗が続き、参加ペアが減少して終焉を迎える。
- しかし捕食者対策を施した営巣林では繁殖成功が確認され、参加個体数の回復事例も得られた。
- 種内干渉の頻度や繁殖成功率との関係から、トキのコロニーは「成長と崩壊」の動態を繰り返す可能性が示唆される。
感想:
- 成長と崩壊は他にもアナロジーがありそう。その深いところで相同なメカニズムがあるんでしょうね。
トキ飼育下個体群の遺伝的多様性の近年における推移
発表者
角野歩夏(新潟大院自然科学)・南澤夏奈香(新潟大農)・石井森昭(新潟大院自然科学)ほか
結果と考察
- トキ始祖個体数7羽、飼育下で生まれた個体数850羽以上
- 飼育下トキ個体群(始祖7羽由来)の血統情報を1999〜2023年で解析し、特に直近数年間を詳細評価。
- ジーン・ドロッピング・シミュレーションにより、始祖ごとの遺伝的寄与率は年次で変動するものの、確率分布は時間とともに裾野が広がる傾向。
- 遺伝子の消失確率・消失危険性は総じて改善し、遺伝的多様性は微増。
- ただし始祖個体ごとの差は大きく、2018年導入の最新始祖の寄与率向上が今後の課題。
- 飼育下個体群の遺伝的基盤は安定化の兆しが見られるが、導入個体の活用戦略が鍵となる。
サンジャクの捕獲事例と外来種管理
発表者
天野一葉(琵琶博)
結果と考察
- サンジャク(カラス科、原産:中国〜インドシナ)は2000年以降、四国西部に定着し分布拡大中。昆虫・小動物・果実・他鳥類の卵や雛を捕食し、生態系や農業への影響が懸念される。
- 愛媛県で「侵略的外来生物」、高知県で「防除対策外来種」に指定。だが警戒心が強く、情報不足で具体的対策は進んでいない。
- 高知県での混獲事例を調査した結果、箱わなの設置環境・季節・餌の種類によって捕獲効率が異なることが確認された。
- これらの知見は、今後のサンジャク管理・防除方策を検討する上で重要な基盤となる。
感想:
- (演者も言われていましたが)サンジャクが増えることの影響評価が圧倒的に足りていない感じを受けました。
福井県におけるソウシチョウの侵入・定着プロセス
発表者
出口翔大(福井市自然史博)・三原学(鳥類標識協会)・吉田一朗(鳥類標識協会)・佐藤文男(山階鳥研)・澤祐介(山階鳥研)
結果と考察
- 福井県での初記録は2006年秋(成鳥標識)、2013年にも雄幼鳥が記録されたが、その後は途絶。
- 2016年以降は観察で毎年秋に確認され、2020年以降は繁殖期(5〜8月)の記録も増加。
- 標識調査では2017〜2021年にほぼ毎年秋に記録され、2022年・2024年には抱卵斑を持つ成鳥や巣立ち幼鳥を確認。
- これらから福井県での本格的な侵入・定着は2017年前後と推定される。
- プロセスとしては、まず越冬期に行動範囲を拡大し、その後繁殖期に定着するパターンが明らかになり、他地域の傾向とも一致した。
感想:
- 標識調査での捕獲が野外観察に先行するという例とお話がありましたが、たまたまな気もします。知らない声を聞いたら録音するのがいいですね。
ニュウナイスズメの繁殖生態 ― 一巣の価値に着目して
発表者
佐々木未悠(総研大)・高橋雅雄(岩手県博)・蛯名純一(おおせっか)・東信行(弘大)・沓掛展之(総研大)
結果と考察
- 2018〜2021年、青森県三沢市で巣箱調査・個体識別・ビデオ撮影を実施。
- 標識個体38羽中、30羽は年1回のみ繁殖。再繁殖は3羽、二回繁殖は5羽。
- 配偶システムは1例の一夫二妻を除き、社会的一夫一妻制。
- ニュウナイスズメは繁殖期が短く、一巣あたりの相対的価値が高いため防衛行動が強いと考えられる。
- これはスズメ(年複数回繁殖・防衛弱い)との違いを説明する要因であり、防衛行動の進化的背景理解に資する。
感想
- 繁殖ピークがニュウナイスズメ2回、スズメ3回とのこと。初回は餌増加に合致していると思いますが、2回目以降のピークは何に同期しているのでしょう?
岩手県南部におけるクマゲラ繁殖の可能性
発表者
藤井忠志・○籠島恵介・阿部恵彦・金沢聡・佐藤和義・原勝雄・原由美(本州産クマゲラ研究会)
結果と考察
- 北海道とは遺伝的交雑がない。
- 本州で繁殖確認は白神山地など4地域のみ。岩手南部でも目撃・巣穴痕跡があるが繁殖実態は未確認。
- 地域の個体群は脆弱で、発電計画や観光開発による影響が懸念される。
- 既知の巣穴8ヶ所の精査と現地調査を実施。今後はコールバック調査や録音データ解析で繁殖の有無を確認予定。
- ICR:DR05でペットボトルに入れる。クマ対策で細い幹の木にいれた。
- Cornell大学のサイトで判定を使っている。セミ、雨音で誤判定
鳥は種子を何個ずつばら撒く? ― 鳥散布における種子配置パターン
発表者
○大河原恭祐(金沢大)・木村一也(石川県森林組合)・佐藤文男(山階鳥研)
結果と考察
- 2005〜2016年に福井県で果実食鳥17種・2214個体の排泄物を調査し、60種・2万1518個の種子を採集。
- 1回の排出あたりの平均は9.7個だが、最頻値は1個で、単独散布が高頻度。
- GLMM解析の結果、小型鳥×大型果実(少数種子)の組み合わせで1個散布が多い傾向。
- 一部植物種では、単独散布に適した果実形態が進化している可能性がある。
- 小鳥5種(メジロ、ヒヨドリ、シロハラ、マミチャジナイ、ルリビタキ?)が種子散布トップ5で、一つずつ排泄していた
- アカメガシワ、カラスザンショウ;果肉は少なくタネは大きい
- カラスも1個の種を含む排泄が多かった。
感想:
- 今回も鳥トリビアとして抜群に面白かったです。種は一個ずつうんちに入るのが一番多いんですって。
富士山の火山荒原におけるヨタカの分布環境要因
発表者
水村春香(富士山研)・上田恵介(立教大)・安田泰輔(富士山研)
結果と考察
- 富士山の火山荒原でプレイバック法によりヨタカの分布を調査。
- ロジスティック回帰分析の結果、傾斜が緩い場所ほどなわばり形成が確認された。
- 草地パッチと火山荒原は急傾斜が多く、土地利用よりも斜度が主要な制限要因となる可能性が示唆された。
- 火山と雪崩が自然撹乱で選好している
- ヨタカの音声録音&分析を進めている
感想:
- 今後について、富士山裾野に70個ぐらいICレコーダを仕掛けておられるみたいなので、分析方法含めて今後が楽しみです。
登山者向けアプリを活用したライチョウ目撃情報収集
発表者
○小林篤(環保研)・松本英高(ヤマップ)・福田真(環境省)
結果と考察
- 環境省とヤマップ(YAMAP)の連携により、登山アプリ投稿からライチョウ情報を収集。
- 2021年9月〜2023年3月の約1年半で8000件超の投稿を抽出し、精査の結果5664件がライチョウと確認。
- 繁殖確認実績のある116山岳のうち、93山岳で繁殖を確認。
- 登山者の公開記録を活用することで、従来困難だった広域・網羅的な分布把握が可能となり、保全地域の特定に有効であることが示された。
- 課題:隠蔽色のAI認識
ポスターで印象深かったもの
Text-to-Audio AI による鳥類音声進化モデルと性選択
発表者
鈴木麗璽・Hao Zhao・有田隆也(名大)
結果と考察
- Stable Audio Open 1.0 をオオルリ録音で追加学習し、多様な「オオルリ風の歌」を生成。
- BirdNETでの分類では、実際の鳴き声に近い音響特徴を持つと判定される傾向を確認。
- 鳴き声を「遺伝子」、選好性を「遺伝子」として持つ個体群を仮想構築。
- メスは自身の選好性と類似した鳴き声を出すオスを選ぶ。
- 予備実験により、鳴き声の多様化と棲み分けの進化がシミュレーション上で再現可能と示唆。
- 今後はフィールド観測との統合で、AIによる進化現象理解の新たな手法となる可能性がある。
感想:
- 鈴木先生らしいご研究。
- ノジコの方言の録音の進化的現象理解の適用可能性についてお話しできました。また相談しようっと。
ミャンマーの複雑な環境がもたらすヒヨドリ科鳥類の種分化
発表者
楢橋真理環(九大)・吉川夏彦・長太伸章・蛭田眞平(国立科博ほか)
結果と考察
- ヒヨドリ科3属7種111個体を対象に、mtDNAと核SNPsで比較系統地理解析を実施。
- シリアカヒヨドリと姉妹種、コウラウンとエボシヒヨドリで、中央平原を境に東西での遺伝的分化を確認。
- ミミジロヒヨドリ種群では、テナセリム山地による隔離が固有種分化を支えたとする先行研究を支持。
- これらの結果から、地理的障壁(中央平原・山地)と環境差が、ヒヨドリ科における種内外の遺伝的分化を促してきたことが明らかになった。
感想:
- 種分岐が起こったタイミングと地質学年代での環境や出来事とマッチできると進化のストーリーがよりクリアに見えて面白そう
川崎市周辺におけるガビチョウのさえずり多様性
発表者
長谷川れい・北村亘(東京都市大)
結果と考察
- 川崎市周辺5地点で20個体のさえずりを収集(2025年5〜7月)。
- 1個体から最大47音節を確認。ウグイスやコジュケイの模倣音も含まれた。
- 音節カタログとパターン分析から、本種の多様で複雑な音節構造を可視化。
- 在来鳥類との周波数帯の一致度も分析し、外来種としての音声的影響の可能性を示唆。
感想:
- 今年5月に発案しての報告ということでしたが、ガビチョウの賑やかさとレパートリーの多さ、囀り風の鳴き声が年中聞かれることから、小鳥の地鳴きと同じコミュニケーションの機能があるのかもしれません。
3音響管モデルによるハシブトガラス声道模型の検討
発表者
木原優太・高橋義典(工学院大)
結果と考察
- 目的: カラスの声道形状に基づく音響モデルと声道模型の実現。
- 方法: ハシブトガラス ka コールをケプストラム処理し、音源周期とフォルマントを解析。
- モデル: 口腔・気管・鳴管を3音響管として接続し、フォルマント周波数を推定。
- 結果:
- 人間の声道のような中央のくびれはなく、複数の気柱共鳴で説明可能。
- 実測フォルマントとモデルは整合。
- 応用: オス個体の発声器官データから付加製造による声道模型を試作。
感想:
- 古生物(恐竜)の鳴き声再現も研究の狙いの一つということでしたので、鳥類進化でどの時期に複雑な音声コミュニケーションを発達させたか、系統的にわかってくると面白いでしょうね。
天は二物を与えるか?―ホオジロの番い形成成功要因―
発表者
松浦志穂・大河原恭祐(金沢大)
結果と考察
- 2023〜2025年に金沢市・医王山でテリトリー雄22羽以上を調査。
- 番い形成成功は特に頭頂部の色彩形態と有意に関係。
- 囀りの特徴(シラブル数・ソングタイプ数)とも相関が見られた。
- 装飾形態と囀りが相互に関連しつつ番い形成に影響する可能性を示唆。
感想:
- 天は二物は与えず視覚が優勢と会場では仰っておられたが、メスが配偶者決定時期と営巣以降の縄張り防衛の囀りに差があるのか(季節変化)は調べられていないとのこと。囀り変化は結晶化以降は変わらないというのが通説ですが、ホオジロでもそうなのか調べないとわからないとも思いました。
以上